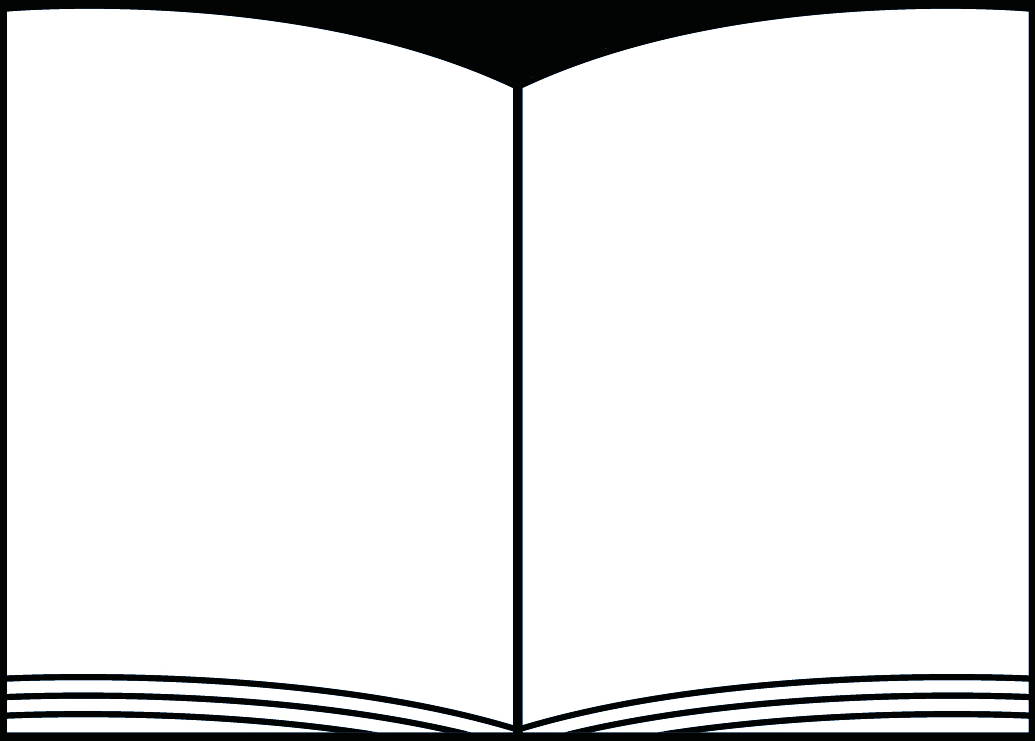詳細画面
資料番号
He006
分類
H . 年史・社史/歴史 /
e . 歴史一般
タイトル
TREND2000 情報コミュニケーションの100年
著者/編者
凸版印刷株式会社エディトリアル研究室 編,凸版印刷株式会社年史センター 編,トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社 編
出版社
凸版印刷
出版日付
2000/04/01
形態
A5判256頁
資料の種別
■年史・社史/歴史
配架場所
図書館内
目次
発刊の辞 / 藤田弘道[凸版印刷株式会社 代表取締役社長]
1900
博覧会:4800万人を魅了した文明祝福の祭典;吉見俊哉
1901
無線技術:通信は無線に、放送は有線に;月尾嘉男
1992
|発掘:メディアを通じた新しい「発掘」;小山修三
1903
飛行機:ライト兄弟初飛行の陰で涙した日本人;斉藤茂太
1904
百貨店:デパートメントストア宣言;山本武利
1905
相対性理論:ただ一人の教授だけがその論文に注目した;村上陽一郎
1906
著作権:グローバル化の中で重要度を増す;倉田喜弘
1907
芸術運動:世界的文化交流から生まれたキュビズム;海野弘
1908
百科事典:徹底した口語体で実践的な項目立て;荒俣宏
1909
新素材:クモの糸より細く、鋼鉄より強く;森谷正規
1910
集合住宅:使いこなしと「すまう文化」;佐藤滋
1911
フェミニズム:M子への私信-平塚らいてうの反逆
1912
ヒーロー:ターザンの登場とスーパーヒーローたち;小野耕世
1913
映画:多くの裏方に支えられてきたハリウッド;おすぎ
1914
自動車:質量を生み出すものが画期的な技術だ;徳大寺有恒
1915
新聞:夕刊は、日本人のライフスタイルを変えた;田村紀雄
1916
広告文化:広告は一人のゲーテを生み出せるか;赤塚行雄
1917
ジャズ:自己主張と「和」の融合;ピーター・バラカン
1918
菓子:ときにコミュニケーションの大道具、小道具に;石井淳蔵
1919
生活とデザイン:創造的社会共同体にしてデザインの運動体;向井周太郎
1920
ラジオ:マイクがこわくなくなった日本人;高橋圭三
1921
単位:文化のなかの単位;森毅
1922
近代建築:ライトが遺してくれたもの;安藤忠雄
1923
自然災害:歴史の教えを活かす;根本順吉
1924
象:天気図がお茶の間に届くようになるまで;倉嶋厚
1925
カメラ:ライカが古くならない謎;田中長徳
1926
ファッション:元気な日本女性の象徴、モガ;大内順子
1927
絵本:いつも読者が王様;やなせたかし
1928
TV技術:笑えば笑ったように;日本ビクター株式会社広報室
1929
国内旅行:人々を旅行へと駆り立てるもの;小林英俊
1930
地下鉄:日本人はなぜ地下街を好むのか;杉村暢二
1931
ダブル・スタンダード:東京・福井間ダブルスタンダード考;山根一眞
1932
笑い:チャップリンと渥美清;山田洋次
1933
教科書:賛否両論の花が咲いた「サクラ読本」;藤村恵
1934
銀座|銀座に乗り遅れる;村松友視
1935
文学賞:一流への登竜門;川西政明
1936
翻訳:危うし、翻訳大国日本;井上一馬
1937
プロ野球:日本職業野球の長男と次男;山藤章二
1938
パニック:パニックの生理;養老孟司
1939
ジャポニズム:ブルーノ・タウトの再発見;井上章一
1940
サラリーマン:サラリーマンよ、真のビジネスマンたれ;日下公人
1941
探知機:彼を知らずして己を知らば・・・;小川和久
1942
戦争とメディア:メディアという武器;柏木博
1943
文具:20世紀の「矢立」;森本哲郎
1944
日記:日記の好きな日本人;川本三郎
1945
宝くじ:焦土に咲いた夢の花;首藤堯
1946
通貨:戦後の円の原点「新円切り替え」;冨田昌宏
1947
教育:いまこそ教育基本法の理念に立ち返れ;堀田力
1948
図書館:女子の閲覧する人、一人もあらざる;紀田順一郎
1949
コンピュータ:プログラム内蔵方式による汎用性獲得;坂村健
1950
キャラクター:ひとつの日米文化比較論;デープ・スペクター
1951
日本映画:あんなわけのわからんものが・・・;白井佳夫
1952
パッケージデザイン:「ピース」とレイモンド・ローウィ;栄久庵憲司
1953
電話:意志疎通の手段から情報処理機器へ;唐津一
1954
テレビ:針を刺して数えろ;猪瀬直樹
1955
アメリカン・カルチャー:アメリカ文化の手ざわり
1956
経済白書:もはや戦後ではない;金森久雄
1957
地球観測:日本、国際地球観測年に参加す;坂田俊文
1958
インスタント食品:TVディナーとチキンラーメン;森枝卓士
1959
週刊誌:「ひと」を通して「ひと」を語る;筑紫哲也
1960
写真:この写真集だけはザラ紙で作りたかった;飯沢耕太郎
1961
ヒット曲:「スキヤキ」誕生前史;玉置宏
1962
エコロジー:環境主義の幕を開けた「沈黙の春」;石弘之
1963
流行語:流行語は世相の波がしら;稲垣吉彦
1964
ポスター:視覚情報文化の親善使節;福田繁雄
1965
海外旅行:おすすめしたい孫と祖父母の海外旅行;兼高かおる
1966
ビートルズ:ビートルズは6月にやってきた;浅井慎平
1967
玩具:新旧のモノが融合する21世紀;北原照久
1968
カタログ:モノを配列することによるメッセージ;石川次郎
1969
宇宙:宇宙からの中継;秋山豊寛
1970
クラスマガジン:「美意識の世代」誕生;甘糟章
1971
外食産業:食卓そのものが外食産業の舞台;大橋照枝
1972
小型化:電子社会を切りひらいた電卓戦争;相田洋
1973
アイドル:三人で競う、トリオで売れる;梨元勝
1974
小売り:流通イノベーション-新しい常識の時代;村田昭治
1975
コピー:四半世紀のコピー論議;名和小太郎
1976
デファクトスタンダード:デファクトスタンダードとデジューリスタンダード;柏木寛
1977
KARAOKE:今後の鍵は高次元自己刺激快感にどこまで迫るかだ;山城祥二
1978
ワープロ:日本語が難しかった日本語ワープロ;森健一
1979
ヒット商品:個人主義を先取りしたウォークマン;山岸由敦
1980
情報革命:情報革命から知識革命へ;野中郁次郎
1981
ベストセラー:ベストセラーの方程式;井狩春男
1982
カード社会:1982年、情報社会始まる;谷口正和
1983
テーマパーク:夢と魔法の王国のソフト戦略;山田五郎
1984
パソコン:メニューからコマンドを選んで動かす;西和彦
1985
テレビゲーム:ネクスト・ステージはモバイルだ;高城剛
1986
フィルム:脇役を主役にした逆転の発想;持田光義
1987
バブル経済:バブル経済の教訓が活かされていない;竹中平蔵
1988
通信:デジタル情報化の望ましい進化;石井威望
1989
マルチメディア:“人間のマルチ化”がもたらすマルチメディア革命;竹村真一
1990
メセナ活動:すべては一本の電話から始まった;福原義春
1991
リサイクル:リサイクルの哲学-蛇口を締めよう;鈴木孝夫
1992
インターネット:情報マッチングと信用付与の時代がくる;金子郁容
1993
世界遺産:文化財赤十字の精神で国際貢献しよう;平山郁夫
1994
CALS:モノづくりの電子情報化;馬場靖憲
1995
日本人ヒーロー:常識を貫いた男、野茂英雄;玉木正之
1996
ジャパニメーション:「ソフト文化」としての「アニメ」;フレデリック・ショット
1997
ワークスタイル:携帯電話はワークスタイルを変えるか;西垣通
1998
天体観測:21世紀の宇宙を望む「すばる」;小尾信彌
1999
ロボット:ホメロスの夢の実現に向かって;舘璋
2000
印刷:新しい統合と文節へ;松岡正剛
インタビュー:情報、コミュニケーションそして未来;ニコラス・ネグロポンテ
寄稿:「コンピュータ騒ぎ」が収まるのを待ちかねて;ブラン・フェレン
執筆者プロフィール/写真提供一覧/参考文献一覧/資料提供・取材協力一覧
1900
博覧会:4800万人を魅了した文明祝福の祭典;吉見俊哉
1901
無線技術:通信は無線に、放送は有線に;月尾嘉男
1992
|発掘:メディアを通じた新しい「発掘」;小山修三
1903
飛行機:ライト兄弟初飛行の陰で涙した日本人;斉藤茂太
1904
百貨店:デパートメントストア宣言;山本武利
1905
相対性理論:ただ一人の教授だけがその論文に注目した;村上陽一郎
1906
著作権:グローバル化の中で重要度を増す;倉田喜弘
1907
芸術運動:世界的文化交流から生まれたキュビズム;海野弘
1908
百科事典:徹底した口語体で実践的な項目立て;荒俣宏
1909
新素材:クモの糸より細く、鋼鉄より強く;森谷正規
1910
集合住宅:使いこなしと「すまう文化」;佐藤滋
1911
フェミニズム:M子への私信-平塚らいてうの反逆
1912
ヒーロー:ターザンの登場とスーパーヒーローたち;小野耕世
1913
映画:多くの裏方に支えられてきたハリウッド;おすぎ
1914
自動車:質量を生み出すものが画期的な技術だ;徳大寺有恒
1915
新聞:夕刊は、日本人のライフスタイルを変えた;田村紀雄
1916
広告文化:広告は一人のゲーテを生み出せるか;赤塚行雄
1917
ジャズ:自己主張と「和」の融合;ピーター・バラカン
1918
菓子:ときにコミュニケーションの大道具、小道具に;石井淳蔵
1919
生活とデザイン:創造的社会共同体にしてデザインの運動体;向井周太郎
1920
ラジオ:マイクがこわくなくなった日本人;高橋圭三
1921
単位:文化のなかの単位;森毅
1922
近代建築:ライトが遺してくれたもの;安藤忠雄
1923
自然災害:歴史の教えを活かす;根本順吉
1924
象:天気図がお茶の間に届くようになるまで;倉嶋厚
1925
カメラ:ライカが古くならない謎;田中長徳
1926
ファッション:元気な日本女性の象徴、モガ;大内順子
1927
絵本:いつも読者が王様;やなせたかし
1928
TV技術:笑えば笑ったように;日本ビクター株式会社広報室
1929
国内旅行:人々を旅行へと駆り立てるもの;小林英俊
1930
地下鉄:日本人はなぜ地下街を好むのか;杉村暢二
1931
ダブル・スタンダード:東京・福井間ダブルスタンダード考;山根一眞
1932
笑い:チャップリンと渥美清;山田洋次
1933
教科書:賛否両論の花が咲いた「サクラ読本」;藤村恵
1934
銀座|銀座に乗り遅れる;村松友視
1935
文学賞:一流への登竜門;川西政明
1936
翻訳:危うし、翻訳大国日本;井上一馬
1937
プロ野球:日本職業野球の長男と次男;山藤章二
1938
パニック:パニックの生理;養老孟司
1939
ジャポニズム:ブルーノ・タウトの再発見;井上章一
1940
サラリーマン:サラリーマンよ、真のビジネスマンたれ;日下公人
1941
探知機:彼を知らずして己を知らば・・・;小川和久
1942
戦争とメディア:メディアという武器;柏木博
1943
文具:20世紀の「矢立」;森本哲郎
1944
日記:日記の好きな日本人;川本三郎
1945
宝くじ:焦土に咲いた夢の花;首藤堯
1946
通貨:戦後の円の原点「新円切り替え」;冨田昌宏
1947
教育:いまこそ教育基本法の理念に立ち返れ;堀田力
1948
図書館:女子の閲覧する人、一人もあらざる;紀田順一郎
1949
コンピュータ:プログラム内蔵方式による汎用性獲得;坂村健
1950
キャラクター:ひとつの日米文化比較論;デープ・スペクター
1951
日本映画:あんなわけのわからんものが・・・;白井佳夫
1952
パッケージデザイン:「ピース」とレイモンド・ローウィ;栄久庵憲司
1953
電話:意志疎通の手段から情報処理機器へ;唐津一
1954
テレビ:針を刺して数えろ;猪瀬直樹
1955
アメリカン・カルチャー:アメリカ文化の手ざわり
1956
経済白書:もはや戦後ではない;金森久雄
1957
地球観測:日本、国際地球観測年に参加す;坂田俊文
1958
インスタント食品:TVディナーとチキンラーメン;森枝卓士
1959
週刊誌:「ひと」を通して「ひと」を語る;筑紫哲也
1960
写真:この写真集だけはザラ紙で作りたかった;飯沢耕太郎
1961
ヒット曲:「スキヤキ」誕生前史;玉置宏
1962
エコロジー:環境主義の幕を開けた「沈黙の春」;石弘之
1963
流行語:流行語は世相の波がしら;稲垣吉彦
1964
ポスター:視覚情報文化の親善使節;福田繁雄
1965
海外旅行:おすすめしたい孫と祖父母の海外旅行;兼高かおる
1966
ビートルズ:ビートルズは6月にやってきた;浅井慎平
1967
玩具:新旧のモノが融合する21世紀;北原照久
1968
カタログ:モノを配列することによるメッセージ;石川次郎
1969
宇宙:宇宙からの中継;秋山豊寛
1970
クラスマガジン:「美意識の世代」誕生;甘糟章
1971
外食産業:食卓そのものが外食産業の舞台;大橋照枝
1972
小型化:電子社会を切りひらいた電卓戦争;相田洋
1973
アイドル:三人で競う、トリオで売れる;梨元勝
1974
小売り:流通イノベーション-新しい常識の時代;村田昭治
1975
コピー:四半世紀のコピー論議;名和小太郎
1976
デファクトスタンダード:デファクトスタンダードとデジューリスタンダード;柏木寛
1977
KARAOKE:今後の鍵は高次元自己刺激快感にどこまで迫るかだ;山城祥二
1978
ワープロ:日本語が難しかった日本語ワープロ;森健一
1979
ヒット商品:個人主義を先取りしたウォークマン;山岸由敦
1980
情報革命:情報革命から知識革命へ;野中郁次郎
1981
ベストセラー:ベストセラーの方程式;井狩春男
1982
カード社会:1982年、情報社会始まる;谷口正和
1983
テーマパーク:夢と魔法の王国のソフト戦略;山田五郎
1984
パソコン:メニューからコマンドを選んで動かす;西和彦
1985
テレビゲーム:ネクスト・ステージはモバイルだ;高城剛
1986
フィルム:脇役を主役にした逆転の発想;持田光義
1987
バブル経済:バブル経済の教訓が活かされていない;竹中平蔵
1988
通信:デジタル情報化の望ましい進化;石井威望
1989
マルチメディア:“人間のマルチ化”がもたらすマルチメディア革命;竹村真一
1990
メセナ活動:すべては一本の電話から始まった;福原義春
1991
リサイクル:リサイクルの哲学-蛇口を締めよう;鈴木孝夫
1992
インターネット:情報マッチングと信用付与の時代がくる;金子郁容
1993
世界遺産:文化財赤十字の精神で国際貢献しよう;平山郁夫
1994
CALS:モノづくりの電子情報化;馬場靖憲
1995
日本人ヒーロー:常識を貫いた男、野茂英雄;玉木正之
1996
ジャパニメーション:「ソフト文化」としての「アニメ」;フレデリック・ショット
1997
ワークスタイル:携帯電話はワークスタイルを変えるか;西垣通
1998
天体観測:21世紀の宇宙を望む「すばる」;小尾信彌
1999
ロボット:ホメロスの夢の実現に向かって;舘璋
2000
印刷:新しい統合と文節へ;松岡正剛
インタビュー:情報、コミュニケーションそして未来;ニコラス・ネグロポンテ
寄稿:「コンピュータ騒ぎ」が収まるのを待ちかねて;ブラン・フェレン
執筆者プロフィール/写真提供一覧/参考文献一覧/資料提供・取材協力一覧