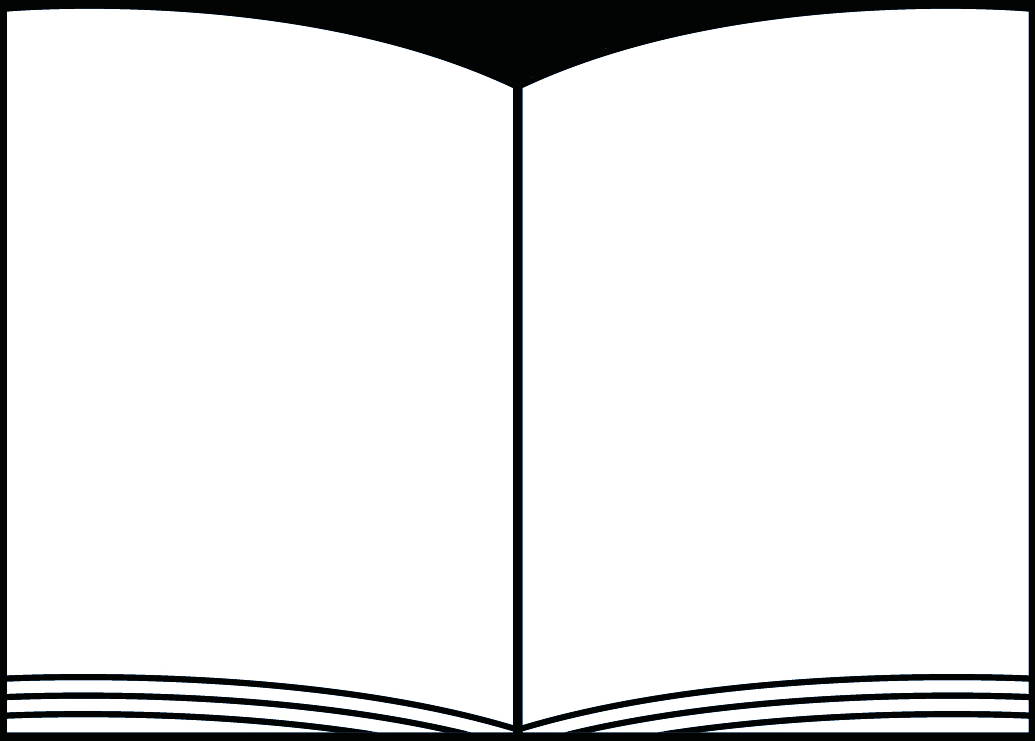詳細画面
資料番号
Ah289
分類
A . プリプレス技術 /
h . 文字
タイトル
日本語活字ものがたり 草創期の人と書体
著者/編者
小宮山博史
出版社
誠文堂新光社
出版日付
2009/01/23
形態
A5判、272頁
資料の種別
■プリプレス技術
配架場所
図書館内
目次
序
第1話 本木昌造・平野富二、危機一髪―幕府輸送船長崎丸2号遭難始末
漂流する幕府輸送船長崎丸2号/八丈島での漂着記録/その後の意外な交流
第2話 明朝体が上海からやってきた―ウイリアム・ギャンブルの来崎
東洋学とキリスト教伝道が明朝体を生む/美華書館の活字販売広告
ウイリアム・ギャンブルの来崎/明朝体、長崎に将来される
第3話 移転を繰り返すミッションプレス―美華書館跡地考
美華書館の上海進出/小東門外に移転/北京路へ/北四川路に印刷工場を新設、そして清算
第4話 四角の中に押し込めること―築地活版の仮名書体
第5話 ゴマンとある漢字―増え続ける漢字数
漢字は何字必要なのか/金属活字ではどの程度文字種を用意していたのか
第6話 漢字に背番号―19世紀のコードポイント
シーボルト来日、そして国外退去/シーボルトの話は、若いオペラ歌手を魅了する/
ホフマン、コール制作の香港活字を導入/ホフマンによる背番号
第7話 Meは横組み、拙者は縦組み―幕末・明治の和欧混植
44歳のアメリカ人派遣宣教医は日本をめざす/ヘボン、上海に滞在する―『和英語林集成』の印刷/
ヘボン、対訳辞書としてはじめて日本語を左横組にする/いまもデザイナーやタイポグラファーを悩ます和欧混植/
前時代のシステムを踏襲した写植書体/デジタルフォントは多言語混植を可能にする
第8話 無名無冠の種字彫師―活字書体を支えた職人達
築地活版最後の彫師 安藤末松/安藤末松聞き書き/彫師の修業は「無言とげんこつ」/
築地活版の彫師 竹口正太郎/築地活版書体の基礎を築いた名人彫師 竹口芳五郎/
最後の地金彫師 清水金之助/終わりのない旅
第9話 毛筆手書きの再現はうまくいくのか―連綿体仮名活字の開発
平野活版の盛況、本木昌造の死/連綿体平仮名活字/平野活版の続き仮名/
ウィーンの王立印刷所、連綿体平仮名活字を開発/復刻のために活字はどのくらい用意されたのか/
ウィーンの連綿体活字、その後
第10話 アイディアは秀、字形は不可―偏傍・冠脚を組み合わせる分合活字
フランス人M.C.グランド分合活字を作る/Legrandの分合活字は世界へ広がる/分合活字はどのくらい彫刻すればよいのか/
分合活字は致命的欠陥を持っていた
あとがき
掲載図版・註・人名一覧
第1話 本木昌造・平野富二、危機一髪―幕府輸送船長崎丸2号遭難始末
漂流する幕府輸送船長崎丸2号/八丈島での漂着記録/その後の意外な交流
第2話 明朝体が上海からやってきた―ウイリアム・ギャンブルの来崎
東洋学とキリスト教伝道が明朝体を生む/美華書館の活字販売広告
ウイリアム・ギャンブルの来崎/明朝体、長崎に将来される
第3話 移転を繰り返すミッションプレス―美華書館跡地考
美華書館の上海進出/小東門外に移転/北京路へ/北四川路に印刷工場を新設、そして清算
第4話 四角の中に押し込めること―築地活版の仮名書体
第5話 ゴマンとある漢字―増え続ける漢字数
漢字は何字必要なのか/金属活字ではどの程度文字種を用意していたのか
第6話 漢字に背番号―19世紀のコードポイント
シーボルト来日、そして国外退去/シーボルトの話は、若いオペラ歌手を魅了する/
ホフマン、コール制作の香港活字を導入/ホフマンによる背番号
第7話 Meは横組み、拙者は縦組み―幕末・明治の和欧混植
44歳のアメリカ人派遣宣教医は日本をめざす/ヘボン、上海に滞在する―『和英語林集成』の印刷/
ヘボン、対訳辞書としてはじめて日本語を左横組にする/いまもデザイナーやタイポグラファーを悩ます和欧混植/
前時代のシステムを踏襲した写植書体/デジタルフォントは多言語混植を可能にする
第8話 無名無冠の種字彫師―活字書体を支えた職人達
築地活版最後の彫師 安藤末松/安藤末松聞き書き/彫師の修業は「無言とげんこつ」/
築地活版の彫師 竹口正太郎/築地活版書体の基礎を築いた名人彫師 竹口芳五郎/
最後の地金彫師 清水金之助/終わりのない旅
第9話 毛筆手書きの再現はうまくいくのか―連綿体仮名活字の開発
平野活版の盛況、本木昌造の死/連綿体平仮名活字/平野活版の続き仮名/
ウィーンの王立印刷所、連綿体平仮名活字を開発/復刻のために活字はどのくらい用意されたのか/
ウィーンの連綿体活字、その後
第10話 アイディアは秀、字形は不可―偏傍・冠脚を組み合わせる分合活字
フランス人M.C.グランド分合活字を作る/Legrandの分合活字は世界へ広がる/分合活字はどのくらい彫刻すればよいのか/
分合活字は致命的欠陥を持っていた
あとがき
掲載図版・註・人名一覧