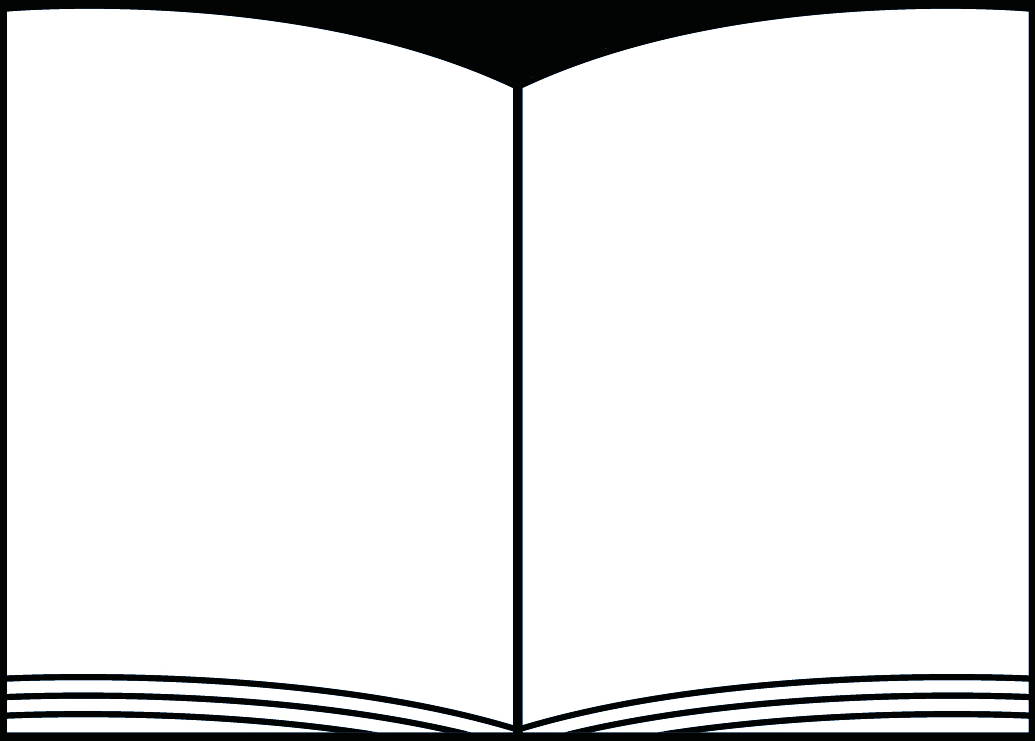詳細画面
資料番号
Fd123
分類
F . 印刷周辺 /
d . 書物・本・文字について
タイトル
日本の漢字・中国の漢字
著者/編者
林 四郎,松岡 榮志
出版社
三省堂
出版日付
1995/07/01
形態
B6判、312頁
資料の種別
■印刷周辺
配架場所
図書館内
目次
まえがき
第一章 日本の漢字・中国の漢字 街角を歩きながら考える―松岡榮志
刺身と生ビール/言語と宇宙/プシュとソーカク/漢字とイメージ/ギャクテとサカテ/刻字と国字/人名と地名/
老舗とニューモード/ハノイの街角で知識と常識/輸入と輸出/琉球と蘇州―南の島にて/
中国の漢字と日本の漢字は調整をはかれるか/
中国の簡体字・日本の新字体 再び「中国の漢字と日本の漢字は共通化できるか」について
第二章 日本語の中の漢字―林 四郎
「一」という字の用法―漢字が運ぶ日本語
基底語から見た日本語漢字の類型
漢字の個性を描く
その1 その類型から個性へ、「愛」の個性
漢字の個性を描く
その2 「者」という字の場合
先人の工夫 一、今昔物語の「白地」
先人の工夫 二、『西国立志篇』の「募化」
先人の工夫 三、近代漢和辞典の新工夫
データベース上の漢字統合
第三章 日本の漢字 いま、常用漢字を見直す―林 大、林 四郎、松岡榮志
日本の漢和辞典のなりたち/部首は漢和辞典のツールとして使えるか/漢和辞典は使われているのか?/
ワープロが肩代わりする漢和辞典の機能/漢字を選択すること、漢字を制限すること/政治も映す漢字制限/
常用漢字表と日本人の言語生活/漢字を使う「主体」はだれなのか/文字改革と国語教育/
文字改革は「ことばなし」ではなかったか/文部省と通産省との谷間市民の「漢 「字」についてのイメージ/
漢字の好みとイメージ/アイデンティティか、わが ままか漢字の「特定する」機能/
名前をどうつけ、どう読むか/漢字の「機」 能度」とはどういうものか/教育漢字の「教育的効果」/
当用漢字制定で作られた字を検証する/日本の当用漢字と中国の簡体字化/字形を制限したことによる混乱/
異体字は統一すべきか/ナベプタの点はくっつくのか?/漢和辞典の新しい「かたち」とは/
異文化理解のための漢和辞典はできないか/漢字と造語力と文字
第四章 中国の漢字 その過去・現在・未来―陳 原、松岡榮志
中国解放前後の社会と出版事情/『新華字典』刊行のいきさつ/文字改革の源流とラテン化新文字運動/
文字改革推進の風潮と魯迅の主張/解放後の文字改革論議/文字改革の究極の目的は漢字の廃止だった/
ローマ字案はどのように作られていったのか/簡化字はどのようにして生まれたか/陳鶴琴の漢字調査と常用字表/
定量分析を、どのように漢字表に反映させるか/周恩来のひとことが簡略化を促進した/
第二次漢字簡化方案を廃止するまで/新たな「通用字 「表」の作成/簡体字化によって部首が変わる?/
簡略化の究極に拼音があるか?/いま、簡略化は本当に必要なのか/パターン認識と繁体字・簡体字
第五章 漢字の未来 言葉・辞典・情報処理―陳 原、林 四郎、林 大、松岡榮志
漢字の過去/漢字政策の潜在意識/漢字の現在当用漢字から常用漢字へ/中国の常用字/
常用漢字と常用語/漢字の将来/外来語と漢字
年表 日本の国語施策・中国の文字改革
「現代漢語常用字表」について―松岡榮志
あとがき
第一章 日本の漢字・中国の漢字 街角を歩きながら考える―松岡榮志
刺身と生ビール/言語と宇宙/プシュとソーカク/漢字とイメージ/ギャクテとサカテ/刻字と国字/人名と地名/
老舗とニューモード/ハノイの街角で知識と常識/輸入と輸出/琉球と蘇州―南の島にて/
中国の漢字と日本の漢字は調整をはかれるか/
中国の簡体字・日本の新字体 再び「中国の漢字と日本の漢字は共通化できるか」について
第二章 日本語の中の漢字―林 四郎
「一」という字の用法―漢字が運ぶ日本語
基底語から見た日本語漢字の類型
漢字の個性を描く
その1 その類型から個性へ、「愛」の個性
漢字の個性を描く
その2 「者」という字の場合
先人の工夫 一、今昔物語の「白地」
先人の工夫 二、『西国立志篇』の「募化」
先人の工夫 三、近代漢和辞典の新工夫
データベース上の漢字統合
第三章 日本の漢字 いま、常用漢字を見直す―林 大、林 四郎、松岡榮志
日本の漢和辞典のなりたち/部首は漢和辞典のツールとして使えるか/漢和辞典は使われているのか?/
ワープロが肩代わりする漢和辞典の機能/漢字を選択すること、漢字を制限すること/政治も映す漢字制限/
常用漢字表と日本人の言語生活/漢字を使う「主体」はだれなのか/文字改革と国語教育/
文字改革は「ことばなし」ではなかったか/文部省と通産省との谷間市民の「漢 「字」についてのイメージ/
漢字の好みとイメージ/アイデンティティか、わが ままか漢字の「特定する」機能/
名前をどうつけ、どう読むか/漢字の「機」 能度」とはどういうものか/教育漢字の「教育的効果」/
当用漢字制定で作られた字を検証する/日本の当用漢字と中国の簡体字化/字形を制限したことによる混乱/
異体字は統一すべきか/ナベプタの点はくっつくのか?/漢和辞典の新しい「かたち」とは/
異文化理解のための漢和辞典はできないか/漢字と造語力と文字
第四章 中国の漢字 その過去・現在・未来―陳 原、松岡榮志
中国解放前後の社会と出版事情/『新華字典』刊行のいきさつ/文字改革の源流とラテン化新文字運動/
文字改革推進の風潮と魯迅の主張/解放後の文字改革論議/文字改革の究極の目的は漢字の廃止だった/
ローマ字案はどのように作られていったのか/簡化字はどのようにして生まれたか/陳鶴琴の漢字調査と常用字表/
定量分析を、どのように漢字表に反映させるか/周恩来のひとことが簡略化を促進した/
第二次漢字簡化方案を廃止するまで/新たな「通用字 「表」の作成/簡体字化によって部首が変わる?/
簡略化の究極に拼音があるか?/いま、簡略化は本当に必要なのか/パターン認識と繁体字・簡体字
第五章 漢字の未来 言葉・辞典・情報処理―陳 原、林 四郎、林 大、松岡榮志
漢字の過去/漢字政策の潜在意識/漢字の現在当用漢字から常用漢字へ/中国の常用字/
常用漢字と常用語/漢字の将来/外来語と漢字
年表 日本の国語施策・中国の文字改革
「現代漢語常用字表」について―松岡榮志
あとがき