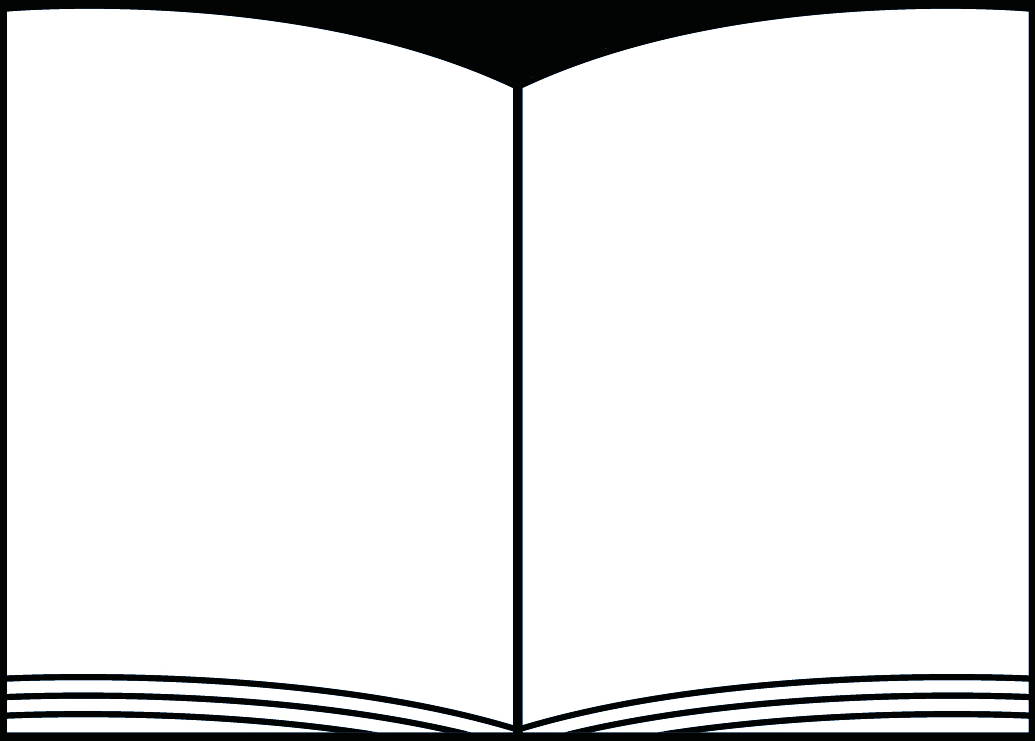詳細画面
資料番号
Hb319
分類
H . 年史・社史/歴史 /
b . 組合史/団体史
タイトル
日本包装技術協会50年史
著者/編者
日本包装技術協会
出版社
日本包装技術協会
出版日付
2013/05/01
形態
A4判 144頁
資料の種別
■年史・社史/歴史
配架場所
図書館内
目次
・創立50周年を迎えて
・祝辞
・目次
●協会の歩み
・設立準備期~設立 昭和38年度(1963年)
日本包装技術協会の設立への機運と設立
誕生した日本包装技術協会がまず目指したもの
・第2年度 昭和39年度(1964年)
関東(東京)、西日本(福岡)、関西(大阪)、中部(名古屋)の4支部を設立
・第3年度 昭和40年度(1965年)
初の総合図書「包装技術便覧」を刊行/日本包装技術士会発足
・第4年度 昭和41年度(1966年)
第1回東京国際包装展(東京パック)開催、閉会式には高松宮殿下同妃殿下がご臨席/
第1期包装管理士講座開催/日本包装管理士会発足/事務所が銀座に移転
・第5年度 昭和42年度(1967年)
北海道支部(札幌)創設/第1回日本パッケージングコンテスト開催/
アジア包装連盟(APF)が東京で設立
・第6年度 昭和43年度(1968年)
新会長に木下氏就任/世界包装機構(WPO)が東京で設立
・第7年度 昭和44年度(1969年)
日本パッケージングコンテストの最高賞にジャパンスター賞を設置
・第8年度 昭和45年度(1970年)
東京パックの出品小間数が1,000小間超/物流への関心高まる
・第9年度 昭和46年度(1971年)
「新包装技術便覧(第1版)」刊行/機関誌「包装技術」が通巻100号/COPE設立・東京パック加盟
・第10年度 昭和47年度(1972年)
「商業包装適正化推進人会」を設立/「包装適正化7原則」を提唱/世界包装会議・東京宣言を発表
・第11年度 昭和48年度(1973年)
創立10周年/北海道支部が札幌パック展を開催/過剰・過大包装是正の消費者運動活発に
・第12年度 昭和49年度(1974年)
日本、ISO/TC122(包装)のPメンバーに/包装管理士講座が札幌会場でも開催
・第13年度 昭和50年度(1975年)
包装管理士講座は第10期/適正包装推進年/西日本支部主催で第1回福岡パック開催
・第14年度 昭和51年度(1976年)
包装管理士が1,000名を突破/包装資材・機械生産出荷額で3兆円超/「包装の歴史」刊行
・第15年度 昭和52年度(1977年)
新会長に丸田氏が就任/第1回「木下賞」開催
・第16年度 昭和53年度(1978年)
国際協力事業団(JICA)との共催で国際包装技術研修コースが始まる/包装懇話会(食品包装)がスタート
・第17年度 昭和54年度(1979年)
第1回訪中団を派遣/第1回包装トップセミナー開催/ユニットロードサイズの標準化に関する調査研究始まる
・第18年度 昭和55年度(1980年)
中国が正式にAPF(アジア包装連盟)に加盟/当会包装技術研究所が開設
・第19年度 昭和56年度(1981年)
新会長に加藤氏が就任/「包装アカデミー」コースがスタート、6名の包装専士誕生/包装のアカデミック組織、「日本包装研究機関連絡会」発足
・第20年度 昭和57年度(1982年)
東京パックが当会単独開催に/清涼飲料用ワンウエイガラスびんが普及
・21年度 昭和58年度(1983年)
創立20周年/東北支部(仙台)設立/加藤会長が世界包装機構(WPO)会長に就任
・第22年度 昭和59年度(1984年)
関東・中部、関西及び西日本の4支部が創設20周年/包装資材・機械生産出荷額が5兆円
・第23年度 昭和60年度(1985年)
新会長に鈴木氏就任/「危険物輸送容器(IBC)の品質基準」が国連勧告となる。
・第24年度 昭和61年度(1986年)
包装管理士講座が6都市で開催/包装管理士は3000名を突破
・第25年度 昭和62年度(1987年)
「食品包装便覧」刊行/「物流バーコートシンボル」JIS化
・第26年度 昭和63年度(1988年)
創立25周年/官民合同による日中包装技術交流会議がスタート/「包装技術」誌が通巻300号/教育用ビデオ「食品包装講座」全6巻を監修
・第27年度 平成元年度(1989年)
新会長に本山氏が就任/JICA大型プロジェクト「アルゼンティン国包装技術協力プロジェクト」始まる/「中部の包装」刊行
・第28年度 平成2年度(1990年)
東京パック‵90の開会式に三笠宮寛仁親王殿下同妃殿下がご臨席/官民共同による日中包装技術交流会が本格化/
包装適正化推進委員会設置/厚生省がごみ非常事態宣言
・第29年度 平成3年度(1991年)
事務所が人形町に転移/“い・い・パックの日”キャンペーンがスタート
・第30年度 平成4年度(1992年)
日本包装学会が創設/アジア包装連盟(APF)設立20周年/包装資材・機械生産出荷額が7兆円超
・第31年度 平成5年度(1993年)
新会長に北島氏が就任/創立30周年/包装管理士が5000名超/「‵93包装白書」刊行
・第32年度 平成6年度(1994年)
事務所が中央区築地東劇ビルに移転/包装憲章及び包装学体系化を提唱
・第33年度 平成7年度(1995年)
第1回「包装新人研修コース」(関東支部)開講/容器包装リサイクル法の説明会に1000名以上」が参加
・第34年度 平成8年度(1996年)
東京パックは新会場「東京ビッグサイト」で開催/欧州包装専門視察団に100名が参加/包装資材・機械生産出荷額が7兆3千億円超
・第35年度 平成9年度(1997年)
新会長に高橋氏が就任/日本パッケージングコンテストが毎年開催になり、最高賞として「通商産業大臣賞」を設置/第1回暮らしの包装商品展
・第36年度 平成10年度(1998年)
国際協力事業団(JICA)から感謝状が授与/JIS「包装貨物―モジュール寸法」制定/EUの“Gateway to Japan”キャンペーン事業への参加
・第37年度 平成11年度(1999年)
ISO 14001の取得増加/JIS見直しの増加
・第38年度 平成12年度(2000年)
包装容器リサイクル法完全施行/包装専士が500名超/21世紀への提言として「持続性ある社会の発展に貢献する包装の実現に向けて」を提唱
・第39年度 平成13年度(2001年)
新会長に江頭氏が就任/会員総数1334(含、個人会員245名)に(50年間で最高数字)
・第40年度 平成14年度(2002年)
全日本包装技術研究大会がだい40回/東北支部創立20周年
・第41年度 平成15年度(2003年)
新会長に三木氏が就任/創立40周年/厚生省・トレーサビリティの導入に向けた施行実施
・第42年度 平成16年度(2004年)
「包装技術」誌が通巻500号/関東、中部、関西、西日本、各支部が創立40周年
・第43年度 平成17年度(2005年)
新会長に鈴木氏が就任/包装管理士講座が第40期、包装管理士は8812名に/当会事業への消費者の参加顕著に
・第44年度 平成18年度(2006年)
日本で初、LAPRI世界包装会議を東京で開催/ISO/TCI122(包装)の国際事務局に
・第45年度 平成19年度(2007年)
新会長に小江氏が就任/国際標準化への功績が認められ経済産業大臣賞を受賞
・第46年度 平成20年度(2008年)
ISO/TCI122総会、東京で開催/日本パッケージングコンテストがだい30回目
・第47年度 平成21年度(2009年)
新会長に足立氏が就任/包装管理士が1万人を突破/経済産業省ロビー展を開催
・第48年度 平成22年度(2010年)
東京パック開催が4日間に変更/臨時総会を開催
・第49年度 平成23年度(2011年)
新会長に池田氏が就任/「公益社団法人日本包装技術協会」誕生/全事業の仕分け/暮らしの包装商品展を新宿駅西口広場で開催
・第50年度 平成24年度(2012年)
●資料編
・JPI歴代会長副会長
・木下賞受賞一覧
・ISO/TC122(包装)の構成及び国内体制
・包装管理士講座カリキュラムの概要
・昭和37年~平成22年までの包装容器・資材出荷金額+包装機械生産金額の合計金額の推移(億円)
・昭和37年~平成22年までの包装容器・資材出荷金額の推移(億円)
・昭和42年~平成22年までの包装容器・資材出荷数量の推移(千トン)
・昭和38年~平成22年までの包装機械生産金額の推移(億円)
・昭和47年~平成22年までの包装機械生産数量の推移(千トン)
・戦後の包装動向/社会・経済の動勢
・祝辞
・目次
●協会の歩み
・設立準備期~設立 昭和38年度(1963年)
日本包装技術協会の設立への機運と設立
誕生した日本包装技術協会がまず目指したもの
・第2年度 昭和39年度(1964年)
関東(東京)、西日本(福岡)、関西(大阪)、中部(名古屋)の4支部を設立
・第3年度 昭和40年度(1965年)
初の総合図書「包装技術便覧」を刊行/日本包装技術士会発足
・第4年度 昭和41年度(1966年)
第1回東京国際包装展(東京パック)開催、閉会式には高松宮殿下同妃殿下がご臨席/
第1期包装管理士講座開催/日本包装管理士会発足/事務所が銀座に移転
・第5年度 昭和42年度(1967年)
北海道支部(札幌)創設/第1回日本パッケージングコンテスト開催/
アジア包装連盟(APF)が東京で設立
・第6年度 昭和43年度(1968年)
新会長に木下氏就任/世界包装機構(WPO)が東京で設立
・第7年度 昭和44年度(1969年)
日本パッケージングコンテストの最高賞にジャパンスター賞を設置
・第8年度 昭和45年度(1970年)
東京パックの出品小間数が1,000小間超/物流への関心高まる
・第9年度 昭和46年度(1971年)
「新包装技術便覧(第1版)」刊行/機関誌「包装技術」が通巻100号/COPE設立・東京パック加盟
・第10年度 昭和47年度(1972年)
「商業包装適正化推進人会」を設立/「包装適正化7原則」を提唱/世界包装会議・東京宣言を発表
・第11年度 昭和48年度(1973年)
創立10周年/北海道支部が札幌パック展を開催/過剰・過大包装是正の消費者運動活発に
・第12年度 昭和49年度(1974年)
日本、ISO/TC122(包装)のPメンバーに/包装管理士講座が札幌会場でも開催
・第13年度 昭和50年度(1975年)
包装管理士講座は第10期/適正包装推進年/西日本支部主催で第1回福岡パック開催
・第14年度 昭和51年度(1976年)
包装管理士が1,000名を突破/包装資材・機械生産出荷額で3兆円超/「包装の歴史」刊行
・第15年度 昭和52年度(1977年)
新会長に丸田氏が就任/第1回「木下賞」開催
・第16年度 昭和53年度(1978年)
国際協力事業団(JICA)との共催で国際包装技術研修コースが始まる/包装懇話会(食品包装)がスタート
・第17年度 昭和54年度(1979年)
第1回訪中団を派遣/第1回包装トップセミナー開催/ユニットロードサイズの標準化に関する調査研究始まる
・第18年度 昭和55年度(1980年)
中国が正式にAPF(アジア包装連盟)に加盟/当会包装技術研究所が開設
・第19年度 昭和56年度(1981年)
新会長に加藤氏が就任/「包装アカデミー」コースがスタート、6名の包装専士誕生/包装のアカデミック組織、「日本包装研究機関連絡会」発足
・第20年度 昭和57年度(1982年)
東京パックが当会単独開催に/清涼飲料用ワンウエイガラスびんが普及
・21年度 昭和58年度(1983年)
創立20周年/東北支部(仙台)設立/加藤会長が世界包装機構(WPO)会長に就任
・第22年度 昭和59年度(1984年)
関東・中部、関西及び西日本の4支部が創設20周年/包装資材・機械生産出荷額が5兆円
・第23年度 昭和60年度(1985年)
新会長に鈴木氏就任/「危険物輸送容器(IBC)の品質基準」が国連勧告となる。
・第24年度 昭和61年度(1986年)
包装管理士講座が6都市で開催/包装管理士は3000名を突破
・第25年度 昭和62年度(1987年)
「食品包装便覧」刊行/「物流バーコートシンボル」JIS化
・第26年度 昭和63年度(1988年)
創立25周年/官民合同による日中包装技術交流会議がスタート/「包装技術」誌が通巻300号/教育用ビデオ「食品包装講座」全6巻を監修
・第27年度 平成元年度(1989年)
新会長に本山氏が就任/JICA大型プロジェクト「アルゼンティン国包装技術協力プロジェクト」始まる/「中部の包装」刊行
・第28年度 平成2年度(1990年)
東京パック‵90の開会式に三笠宮寛仁親王殿下同妃殿下がご臨席/官民共同による日中包装技術交流会が本格化/
包装適正化推進委員会設置/厚生省がごみ非常事態宣言
・第29年度 平成3年度(1991年)
事務所が人形町に転移/“い・い・パックの日”キャンペーンがスタート
・第30年度 平成4年度(1992年)
日本包装学会が創設/アジア包装連盟(APF)設立20周年/包装資材・機械生産出荷額が7兆円超
・第31年度 平成5年度(1993年)
新会長に北島氏が就任/創立30周年/包装管理士が5000名超/「‵93包装白書」刊行
・第32年度 平成6年度(1994年)
事務所が中央区築地東劇ビルに移転/包装憲章及び包装学体系化を提唱
・第33年度 平成7年度(1995年)
第1回「包装新人研修コース」(関東支部)開講/容器包装リサイクル法の説明会に1000名以上」が参加
・第34年度 平成8年度(1996年)
東京パックは新会場「東京ビッグサイト」で開催/欧州包装専門視察団に100名が参加/包装資材・機械生産出荷額が7兆3千億円超
・第35年度 平成9年度(1997年)
新会長に高橋氏が就任/日本パッケージングコンテストが毎年開催になり、最高賞として「通商産業大臣賞」を設置/第1回暮らしの包装商品展
・第36年度 平成10年度(1998年)
国際協力事業団(JICA)から感謝状が授与/JIS「包装貨物―モジュール寸法」制定/EUの“Gateway to Japan”キャンペーン事業への参加
・第37年度 平成11年度(1999年)
ISO 14001の取得増加/JIS見直しの増加
・第38年度 平成12年度(2000年)
包装容器リサイクル法完全施行/包装専士が500名超/21世紀への提言として「持続性ある社会の発展に貢献する包装の実現に向けて」を提唱
・第39年度 平成13年度(2001年)
新会長に江頭氏が就任/会員総数1334(含、個人会員245名)に(50年間で最高数字)
・第40年度 平成14年度(2002年)
全日本包装技術研究大会がだい40回/東北支部創立20周年
・第41年度 平成15年度(2003年)
新会長に三木氏が就任/創立40周年/厚生省・トレーサビリティの導入に向けた施行実施
・第42年度 平成16年度(2004年)
「包装技術」誌が通巻500号/関東、中部、関西、西日本、各支部が創立40周年
・第43年度 平成17年度(2005年)
新会長に鈴木氏が就任/包装管理士講座が第40期、包装管理士は8812名に/当会事業への消費者の参加顕著に
・第44年度 平成18年度(2006年)
日本で初、LAPRI世界包装会議を東京で開催/ISO/TCI122(包装)の国際事務局に
・第45年度 平成19年度(2007年)
新会長に小江氏が就任/国際標準化への功績が認められ経済産業大臣賞を受賞
・第46年度 平成20年度(2008年)
ISO/TCI122総会、東京で開催/日本パッケージングコンテストがだい30回目
・第47年度 平成21年度(2009年)
新会長に足立氏が就任/包装管理士が1万人を突破/経済産業省ロビー展を開催
・第48年度 平成22年度(2010年)
東京パック開催が4日間に変更/臨時総会を開催
・第49年度 平成23年度(2011年)
新会長に池田氏が就任/「公益社団法人日本包装技術協会」誕生/全事業の仕分け/暮らしの包装商品展を新宿駅西口広場で開催
・第50年度 平成24年度(2012年)
●資料編
・JPI歴代会長副会長
・木下賞受賞一覧
・ISO/TC122(包装)の構成及び国内体制
・包装管理士講座カリキュラムの概要
・昭和37年~平成22年までの包装容器・資材出荷金額+包装機械生産金額の合計金額の推移(億円)
・昭和37年~平成22年までの包装容器・資材出荷金額の推移(億円)
・昭和42年~平成22年までの包装容器・資材出荷数量の推移(千トン)
・昭和38年~平成22年までの包装機械生産金額の推移(億円)
・昭和47年~平成22年までの包装機械生産数量の推移(千トン)
・戦後の包装動向/社会・経済の動勢