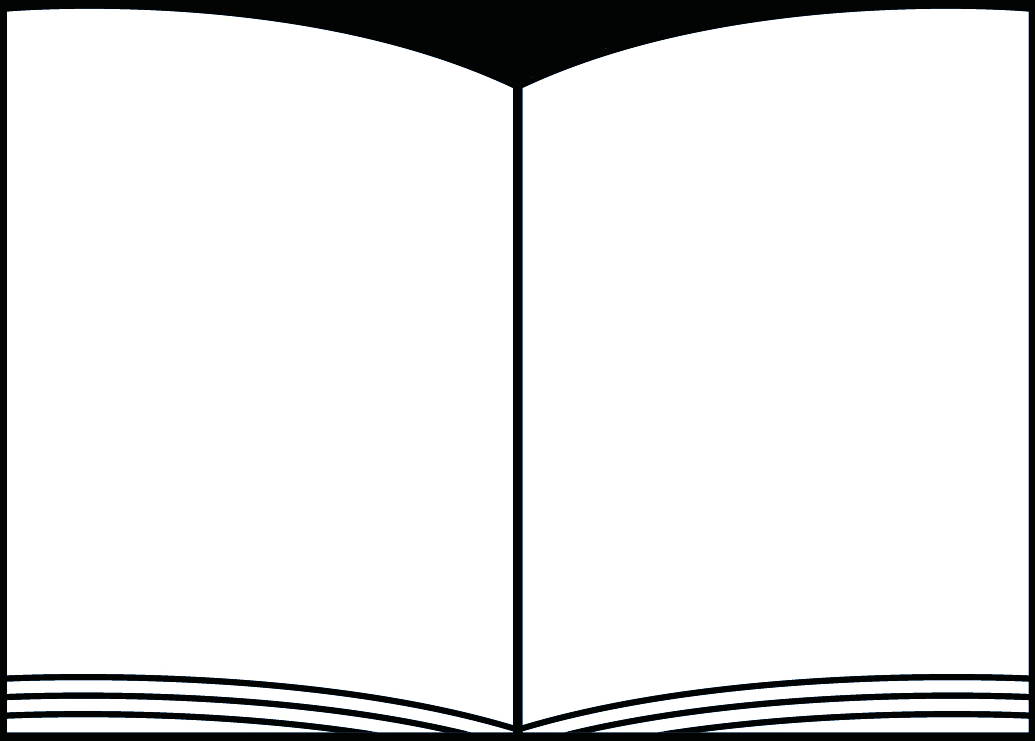詳細画面
資料番号
Ff342
分類
F . 印刷周辺 /
f . 単行本
タイトル
脳を創る読書 なぜ「紙の本」が人にとって必要なのか
著者/編者
酒井邦嘉
出版社
実業之日本社
出版日付
2012/05/25
形態
縦19㎝×横12㎝、200頁
資料の種別
■印刷周辺
配架場所
図書館内
目次
はじめに……それでも紙の本は必要である
1 読書は脳の想像力を高める
活字は脳で音に変換されて、言語野へと送られる/活字は圧倒的に情報量が少ない/
受け取る「入力」の情報量が少ないほど、脳は想像して補う/文の構造を見抜く脳のすごい能力/
書体や記号も活字の重要な要素である/紙の本と電子書籍はアナログとデジタルの違いだけで比較できない/
手書き文字は活字より情報量が多い/伝える「出力」の情報量が多いほど、脳はさらに想像力を高める
2 脳の特性と不思議を知る
あらゆる言語は共通する性質を持っている/「再帰性」は脳が創造する力のもとになる/
マザーグースの「つみあげうた」で答えがすぐ出せる理由/あの名曲にもあった「再帰性」の構造/
数学の得意・不得意は想像力の差 /「単純・対称・意外性」という「美の三要素」/
非対称の美しさは「対称性」が前提にある/「左脳は論理、右脳は感性」は正しいか/「分離脳」の不思議/
鉄腕アトムは現在の技術で作れるか/直線や円を描くには確かな想像力が必要/
想像力が働かないと、記憶することが難しくなる/脳は予想して先読みする/
脳はなぜ行間を読むことができるのか
3 書く力・読む力はどうすれば鍛えられるのか
言語は音声が先で、後から文字が生まれた/日本語が「難しい言語」といわれるのは誤解/
夏目漱石はなぜ「こども」の漢字を使い分けたのか/全文ローマ字書きした日本語も、慣れればすらすら読める!/
電子書籍の違和感はどこに原因があるのか/読書量が多ければ多いほど、言語能力は鍛えられる/
マジックは人の想像力がなせる不思議/想像力が言語コミュニケーションを円滑にする/
女性のほうが行間を読むような想像力に優れている/読書が脳を創る本当の意味
4 紙の本と電子書籍は何がどう違うか
なぜ画面上で見落とした誤字が紙の上では見つかるのか/避けられない電子化の時代に電子書籍をどう扱うか/
それでも「電子」より「紙」の辞書のほうが便利/電子書籍はここが問題/電子化されるときの問題点とは/
紙の本には独自の楽しみがある/紙の本には「初版本」という代えがたい存在がある/オリジナルの自筆原稿は何を語りかけてくるか/
オリジナルの自筆譜から多くのことが読み取れる/手書きの手紙と共通する紙の本の真のよさとは
5 紙の本と電子書籍の使い分けが大切
「電子化」で脳が進化することなど、ありえない/二つの読み方を使い分ければ、「読む力」は鍛えられる/
朗読は心に響く読書である/紙の本と電子書籍のよさをそれぞれ享受すべき/紙の本にはどんな強みがあるか/
電子教科書の三つの利点/電子教科書に「脳を創る」 学問を問う/電子化の波にただ流されないために/
明らかな退行現象をこのまま進めてよいか/人間が作ったものによって人間が堕落するのは避けられないか/
電子化が悪いのではなく、使い方が悪いだけ/オーディオの電子化で失くしたものがある/
写真撮影の電子化は芸術性を損なう場合がある/電子化された人工物を活かすも殺すも、使う側の問題/
1 読書は脳の想像力を高める
活字は脳で音に変換されて、言語野へと送られる/活字は圧倒的に情報量が少ない/
受け取る「入力」の情報量が少ないほど、脳は想像して補う/文の構造を見抜く脳のすごい能力/
書体や記号も活字の重要な要素である/紙の本と電子書籍はアナログとデジタルの違いだけで比較できない/
手書き文字は活字より情報量が多い/伝える「出力」の情報量が多いほど、脳はさらに想像力を高める
2 脳の特性と不思議を知る
あらゆる言語は共通する性質を持っている/「再帰性」は脳が創造する力のもとになる/
マザーグースの「つみあげうた」で答えがすぐ出せる理由/あの名曲にもあった「再帰性」の構造/
数学の得意・不得意は想像力の差 /「単純・対称・意外性」という「美の三要素」/
非対称の美しさは「対称性」が前提にある/「左脳は論理、右脳は感性」は正しいか/「分離脳」の不思議/
鉄腕アトムは現在の技術で作れるか/直線や円を描くには確かな想像力が必要/
想像力が働かないと、記憶することが難しくなる/脳は予想して先読みする/
脳はなぜ行間を読むことができるのか
3 書く力・読む力はどうすれば鍛えられるのか
言語は音声が先で、後から文字が生まれた/日本語が「難しい言語」といわれるのは誤解/
夏目漱石はなぜ「こども」の漢字を使い分けたのか/全文ローマ字書きした日本語も、慣れればすらすら読める!/
電子書籍の違和感はどこに原因があるのか/読書量が多ければ多いほど、言語能力は鍛えられる/
マジックは人の想像力がなせる不思議/想像力が言語コミュニケーションを円滑にする/
女性のほうが行間を読むような想像力に優れている/読書が脳を創る本当の意味
4 紙の本と電子書籍は何がどう違うか
なぜ画面上で見落とした誤字が紙の上では見つかるのか/避けられない電子化の時代に電子書籍をどう扱うか/
それでも「電子」より「紙」の辞書のほうが便利/電子書籍はここが問題/電子化されるときの問題点とは/
紙の本には独自の楽しみがある/紙の本には「初版本」という代えがたい存在がある/オリジナルの自筆原稿は何を語りかけてくるか/
オリジナルの自筆譜から多くのことが読み取れる/手書きの手紙と共通する紙の本の真のよさとは
5 紙の本と電子書籍の使い分けが大切
「電子化」で脳が進化することなど、ありえない/二つの読み方を使い分ければ、「読む力」は鍛えられる/
朗読は心に響く読書である/紙の本と電子書籍のよさをそれぞれ享受すべき/紙の本にはどんな強みがあるか/
電子教科書の三つの利点/電子教科書に「脳を創る」 学問を問う/電子化の波にただ流されないために/
明らかな退行現象をこのまま進めてよいか/人間が作ったものによって人間が堕落するのは避けられないか/
電子化が悪いのではなく、使い方が悪いだけ/オーディオの電子化で失くしたものがある/
写真撮影の電子化は芸術性を損なう場合がある/電子化された人工物を活かすも殺すも、使う側の問題/