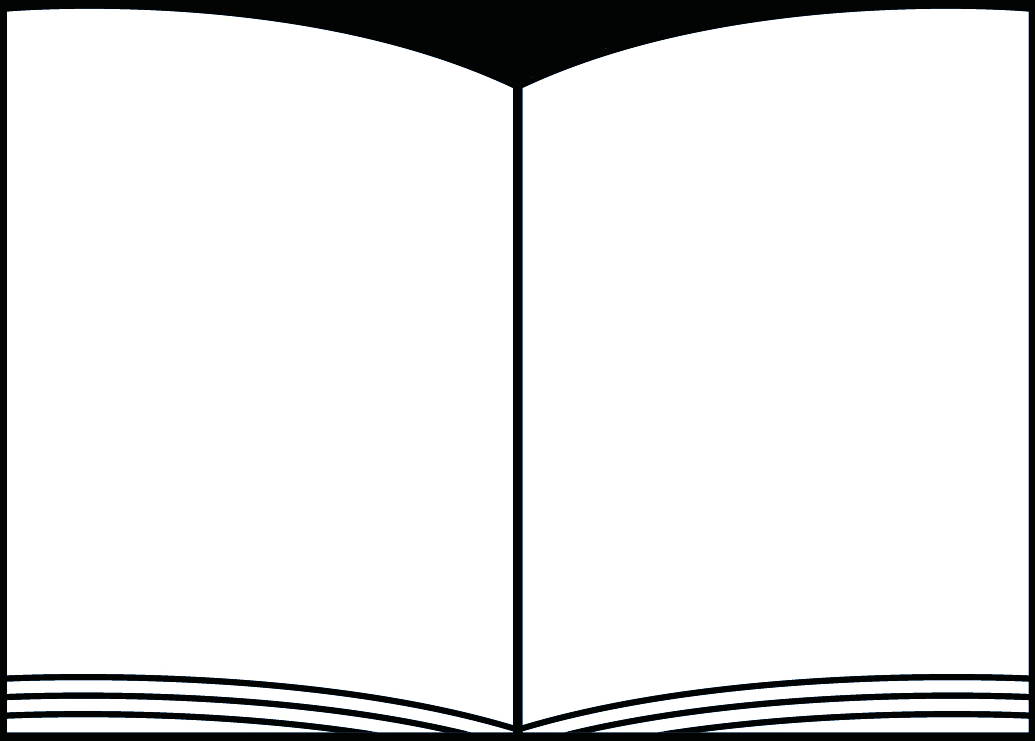詳細画面
資料番号
Fd111
分類
F . 印刷周辺 /
d . 書物・本・文字について
タイトル
「いろは」の十九世紀 文字と教育の文化史 ブックレット<書物をひらく>26
著者/編者
岡田一祐
出版社
平凡社
出版日付
2022/03/25
形態
A5判 104頁
資料の種別
■印刷周辺
配架場所
図書館内
目次
はじめに―文明開化下の文字の変容と初学び
一 「いろは」とはどういうものか
「いろは」の起源/「いろは手本」/「いろは仮名」について
二 寺子屋の「いろは」
1 入門としての「いろは」
寺小屋の興り/寺小屋入門と手習い/「いろは手本」の手習い
2 往来物で学ぶ
『春興手習い出精双六』から見る往来物の推移/往来物の文字/候文は丁寧語の書き言葉
3 寺子屋から学問・芸道の世界へ
学問の世界への羽ばたき/素読・輪講・講釈/芸事・芸道の世界へ
三 西洋人の「いろは」
1 ロニー―仮名活字の製作者
十九世紀日本学の成立/日本学者ロニーの誕生/ロニーと「いろは」
2 ヘボン―日本宣教と辞書
ヘボンの訳業と『和英語林集成』/聖書翻訳と活字/『和英語林集成』と「いろは」
3 チェンバレン―日本学の大成者
帝国大学名誉教師・チェンバレン/日本における日本学/『文字のしるべ』と「いろは」
四 小学校の文字学習
1 「いろは」から「五十音図」へ
小学校の誕生/明治初期の教科書/明治中期以降の教科書と変体仮名
2 小学校で漢字を学ぶ
漢字の数え方の変化/漢字の数え方/漢字の使い方を制限する
3 近代的な小学校へ
小学校は学問を前提とする/明治の新しい言葉/文語体から口語体へ
4 木版本から活字本へ文字の統一
木版本の世界/明治期の活字印刷と文字の整理/文字はなにを伝えるか―文字観の変化
五 「いろは」の十九世紀
「いろは」とその他の文字・教育の十九世紀/「成熟した文字利用者」像の変化と変体仮名
おわりに
あとがきと読書案内
掲載図版一覧
一 「いろは」とはどういうものか
「いろは」の起源/「いろは手本」/「いろは仮名」について
二 寺子屋の「いろは」
1 入門としての「いろは」
寺小屋の興り/寺小屋入門と手習い/「いろは手本」の手習い
2 往来物で学ぶ
『春興手習い出精双六』から見る往来物の推移/往来物の文字/候文は丁寧語の書き言葉
3 寺子屋から学問・芸道の世界へ
学問の世界への羽ばたき/素読・輪講・講釈/芸事・芸道の世界へ
三 西洋人の「いろは」
1 ロニー―仮名活字の製作者
十九世紀日本学の成立/日本学者ロニーの誕生/ロニーと「いろは」
2 ヘボン―日本宣教と辞書
ヘボンの訳業と『和英語林集成』/聖書翻訳と活字/『和英語林集成』と「いろは」
3 チェンバレン―日本学の大成者
帝国大学名誉教師・チェンバレン/日本における日本学/『文字のしるべ』と「いろは」
四 小学校の文字学習
1 「いろは」から「五十音図」へ
小学校の誕生/明治初期の教科書/明治中期以降の教科書と変体仮名
2 小学校で漢字を学ぶ
漢字の数え方の変化/漢字の数え方/漢字の使い方を制限する
3 近代的な小学校へ
小学校は学問を前提とする/明治の新しい言葉/文語体から口語体へ
4 木版本から活字本へ文字の統一
木版本の世界/明治期の活字印刷と文字の整理/文字はなにを伝えるか―文字観の変化
五 「いろは」の十九世紀
「いろは」とその他の文字・教育の十九世紀/「成熟した文字利用者」像の変化と変体仮名
おわりに
あとがきと読書案内
掲載図版一覧