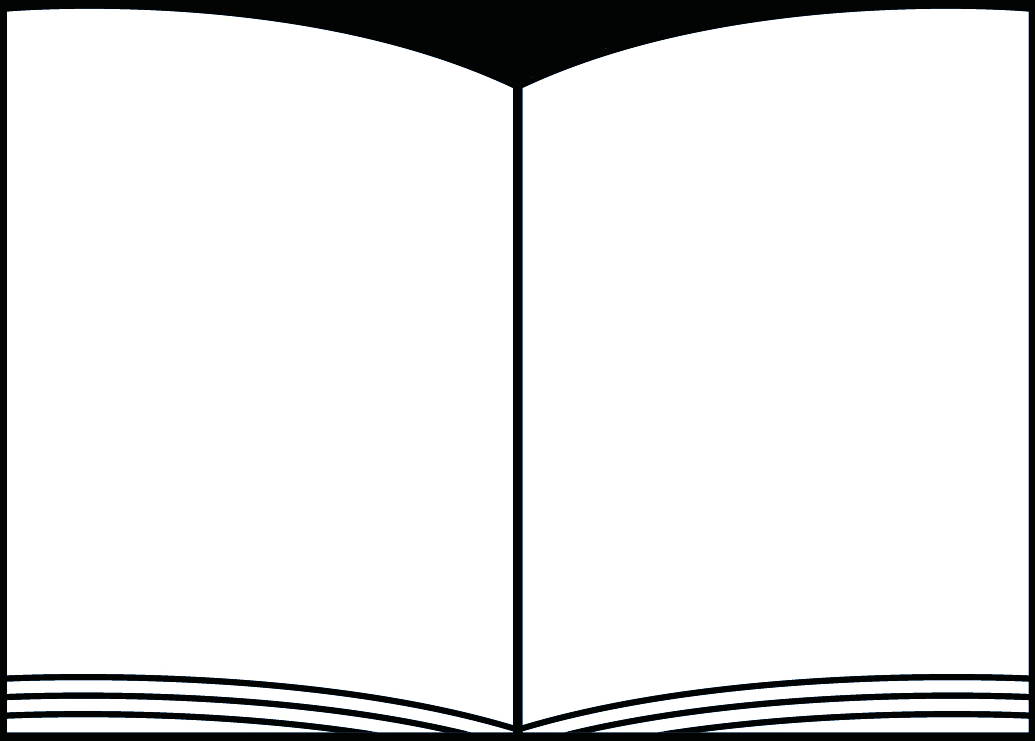詳細画面
資料番号
Fg161
分類
F . 印刷周辺 /
g . 図録・目録
タイトル
武蔵野美術大学コレクション 博物図譜 ―デジタルアーカイブの試み―
著者/編者
特別監修 荒俣博,監修 寺山祐策,編集 本庄美千代
出版社
朝倉書店
出版日付
2018/10/15
形態
26.5㎝×19㎝、508頁
資料の種別
■印刷周辺
配架場所
図書館内
目次
I 図譜編 解説・本庄美千代
I-01 『花蝶珍種図譜』
I-02 『人体構造解剖図集』
I-03 『中国ヨーロッパ植物図譜』
I-04 『第3 次太平洋航海記』
I-05 『イギリスの昆虫』
I-06 『名花素描』
I-07 『ルソーの植物学』
I-08 『オーストラリア探検記』
I-09 『コルディエラ景観図集』
I-10 『フローラの神殿』
I-11 『解剖学遺稿集』
I-12 『熱帯ヤシ科植物図譜』(第1巻、第2巻、第3巻)
I-13 『ユラニー号およびフィジシエンヌ号世界周航記録:動物図譜編』
I-14 『脊椎動物図譜』(哺乳類編、爬虫類編)
I-15 『コキーユ号世界航海記』(動物編、植物編、探検航海編)
I-16 『アストロラブ号世界周航記』
(航海地図、航海史:図録1・図録2、ニュージーランドの動物図譜,哺乳類、軟体動物図譜、動物図譜、植物図譜)
I-17 『一般と個別の頭足類図譜』
I-18 『鳩図譜』
I-19 『チリ全史』
I-20 『八色鳥科鳥類図譜』
I-21 『フウチョウ科・ニワシドリ科鳥類図譜』
I-22 『自然の造形』
I-23 『エルウィズ氏ユリ属の研究補遺』
I-24 『[中国肉筆博物図集]』
II 博物学とその美的表現の歴史 荒俣 宏
Ⅱ-01 博物画の楽しみ
博物誌Naturalis Historiaとは何か/世界を開示する―博物学画像―/怪物画も重宝な資料だった/教育の手本になった博物画家
/記述と図像化に関する3つの方法/分類学の基本概念は相同と相似/博物画は事実と想像の混合物である/博物画は模写される過程でエラーを発生させる
Ⅱ-02 博物採集,博物館,そして博覧会
世界1週航海の結果、博物館が生まれる/北の果て、南の果て、そして真ん中の海/頭が重くてひっくり返りそうな地球インコが鳴く幻想の南極大陸
/ロマンスとパラダイスの島タヒチを巡る争い/キャプテン・クックが開いた新世界/ナポレオンも応募したラ・ペルーズの探検航海/楽園の島での幻滅
/フランスとロシアの追随
Ⅱ-03 日本博物学と図譜の進展―栗本丹洲『千蟲譜』を中心に―
西洋と日本の博物画は異質である/干物か刺身か?/魚はなぜ跳ね上がって描かれるのか?/解剖学と形態学の交差/本物は偽物に間違えられる?
/『千蟲譜』に見える先見性/擬態の問題を意識した丹州/お菊虫の登場/釣りをする魚の観察
Ⅱ-04 視覚の冒険―「水族館の歴史」に寄せて―
繋がっていく関心、開ける展望/万博会場と大温室の結合/ラーケン温室も巨大なレセプション施設だった/ウォーディアン・ケースによる啓示
/ウォードの次なる発見/ロンドン動物園に「フィッシュハウス」出現/ドイツの水族館の「環境展示」/1900年万博は「海産生物様式」の万博でもあった
/自然と人工の美の統合
Ⅱ-05 博物画の現在と過去
博物図は困難な絵である/デューラーも博物図を制作した/体を壊すほどの仕事だった?/それでもアート化する不思議/人類3万年の博物画展を開催できる
/死物を活物に変える努力/植物図譜と実践的な描写/科学革命と図鑑革命の原理―自分の眼で見よ―/豊かで幸福な博物画も生まれた
/奇跡の昆虫図もドイツから/博物画を国の美術にしようとした大帝
Ⅲ 書物からアーカイブへ
Ⅲ-01 美術大学におけるデジタルアーカイブの試みとは 寺山祐策
Ⅲ-02 特装本「博物図譜とデジタルアーカイブ」の発刊について 寺山祐策
Ⅲ-03 博物図譜コレクションのはじまりから研究活用まで:
「荒俣宏旧蔵博物図譜コレクション」をめぐって 本庄美千代
Ⅲ-04 タッチパネル閲覧システムから「MAU M&L 博物図譜」開発まで 大田暁雄・河野通義
人名リスト
参考文献
視覚化される世界「博物図譜とデジタルアーカイブ」参考資料年表 谷田 幸・田中知美
I-01 『花蝶珍種図譜』
I-02 『人体構造解剖図集』
I-03 『中国ヨーロッパ植物図譜』
I-04 『第3 次太平洋航海記』
I-05 『イギリスの昆虫』
I-06 『名花素描』
I-07 『ルソーの植物学』
I-08 『オーストラリア探検記』
I-09 『コルディエラ景観図集』
I-10 『フローラの神殿』
I-11 『解剖学遺稿集』
I-12 『熱帯ヤシ科植物図譜』(第1巻、第2巻、第3巻)
I-13 『ユラニー号およびフィジシエンヌ号世界周航記録:動物図譜編』
I-14 『脊椎動物図譜』(哺乳類編、爬虫類編)
I-15 『コキーユ号世界航海記』(動物編、植物編、探検航海編)
I-16 『アストロラブ号世界周航記』
(航海地図、航海史:図録1・図録2、ニュージーランドの動物図譜,哺乳類、軟体動物図譜、動物図譜、植物図譜)
I-17 『一般と個別の頭足類図譜』
I-18 『鳩図譜』
I-19 『チリ全史』
I-20 『八色鳥科鳥類図譜』
I-21 『フウチョウ科・ニワシドリ科鳥類図譜』
I-22 『自然の造形』
I-23 『エルウィズ氏ユリ属の研究補遺』
I-24 『[中国肉筆博物図集]』
II 博物学とその美的表現の歴史 荒俣 宏
Ⅱ-01 博物画の楽しみ
博物誌Naturalis Historiaとは何か/世界を開示する―博物学画像―/怪物画も重宝な資料だった/教育の手本になった博物画家
/記述と図像化に関する3つの方法/分類学の基本概念は相同と相似/博物画は事実と想像の混合物である/博物画は模写される過程でエラーを発生させる
Ⅱ-02 博物採集,博物館,そして博覧会
世界1週航海の結果、博物館が生まれる/北の果て、南の果て、そして真ん中の海/頭が重くてひっくり返りそうな地球インコが鳴く幻想の南極大陸
/ロマンスとパラダイスの島タヒチを巡る争い/キャプテン・クックが開いた新世界/ナポレオンも応募したラ・ペルーズの探検航海/楽園の島での幻滅
/フランスとロシアの追随
Ⅱ-03 日本博物学と図譜の進展―栗本丹洲『千蟲譜』を中心に―
西洋と日本の博物画は異質である/干物か刺身か?/魚はなぜ跳ね上がって描かれるのか?/解剖学と形態学の交差/本物は偽物に間違えられる?
/『千蟲譜』に見える先見性/擬態の問題を意識した丹州/お菊虫の登場/釣りをする魚の観察
Ⅱ-04 視覚の冒険―「水族館の歴史」に寄せて―
繋がっていく関心、開ける展望/万博会場と大温室の結合/ラーケン温室も巨大なレセプション施設だった/ウォーディアン・ケースによる啓示
/ウォードの次なる発見/ロンドン動物園に「フィッシュハウス」出現/ドイツの水族館の「環境展示」/1900年万博は「海産生物様式」の万博でもあった
/自然と人工の美の統合
Ⅱ-05 博物画の現在と過去
博物図は困難な絵である/デューラーも博物図を制作した/体を壊すほどの仕事だった?/それでもアート化する不思議/人類3万年の博物画展を開催できる
/死物を活物に変える努力/植物図譜と実践的な描写/科学革命と図鑑革命の原理―自分の眼で見よ―/豊かで幸福な博物画も生まれた
/奇跡の昆虫図もドイツから/博物画を国の美術にしようとした大帝
Ⅲ 書物からアーカイブへ
Ⅲ-01 美術大学におけるデジタルアーカイブの試みとは 寺山祐策
Ⅲ-02 特装本「博物図譜とデジタルアーカイブ」の発刊について 寺山祐策
Ⅲ-03 博物図譜コレクションのはじまりから研究活用まで:
「荒俣宏旧蔵博物図譜コレクション」をめぐって 本庄美千代
Ⅲ-04 タッチパネル閲覧システムから「MAU M&L 博物図譜」開発まで 大田暁雄・河野通義
人名リスト
参考文献
視覚化される世界「博物図譜とデジタルアーカイブ」参考資料年表 谷田 幸・田中知美