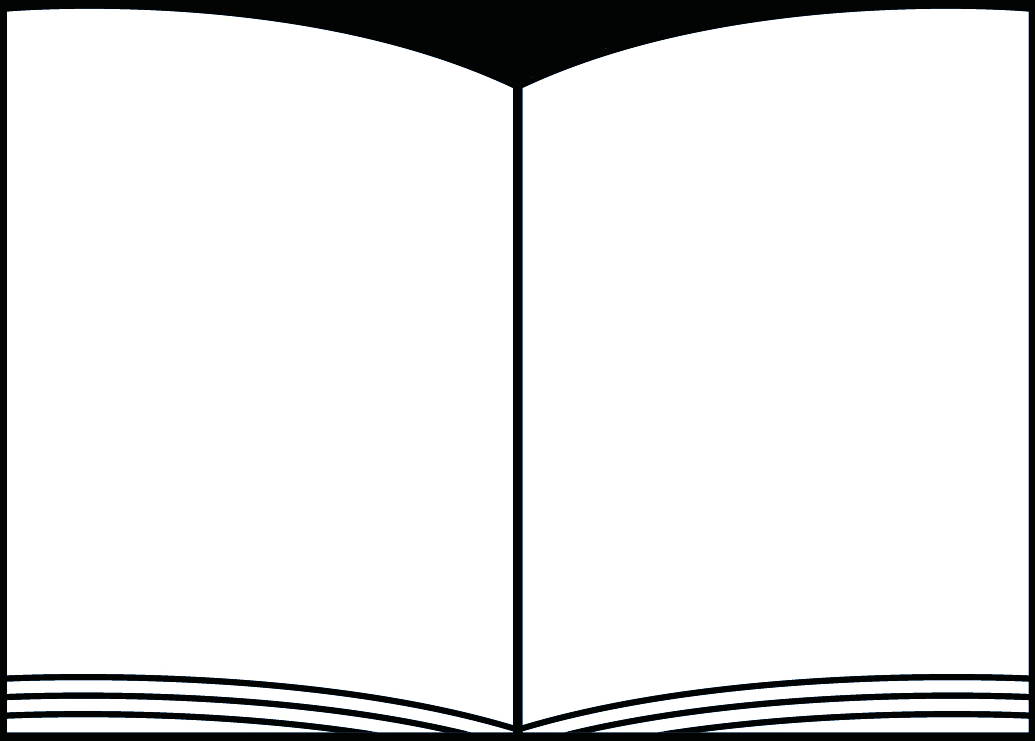詳細画面
資料番号
Fd110
分類
F . 印刷周辺 /
d . 書物・本・文字について
タイトル
近代平仮名体系の成立 明治期読本と平仮名字体意識
著者/編者
岡田一祐
出版社
文学通信
出版日付
2021/02/28
形態
A5判 356頁
資料の種別
■印刷周辺
配架場所
図書館内
目次
第一部 はじめに
第一章 明治期読本の平仮名字体意識の諸問題
一、はじめに
二、明治期の日本語について
二・一 明治期の文字
二・二 近代の語彙・文体と表記
二・三 明治期の識字
二・四 明治期の言語改革論
三、明治期の平仮名について
三・一 明治期と江戸期の対照
三・二 読本以外の出版物における仮名字体
三・二・一 明治期の新聞における字体
三・二・二 明治期の雑誌における字体
三・二・三 小括
三・三 読本における仮名字体
四、明治期の読本について
四・一 読本の時代区分
四・二 読本と仮名字体教授の歴史
四・二・一 前史
四・二・二 自由発行期
四・二・三 調査済教科書表期
四・二・四 検定期
四・二・五 小括
五、おわりに
第二章 いろは仮名の来しかた―近世・近代における平仮名字体の体系化
一、はじめに
二、いろは歌とその仮名
三、近世までの平仮名の体系と非体系性
四、近代初等教育でのいろは仮名と体系化
五、活版印刷における字体数削減と仮名の画一化
六、おわりに
第二部 近世の仮名字体意識の諸問題
第三章 江戸期のいろは仮名
一、はじめに
二、先行研究
三、いろは歌手本の仮名
四、君臣歌の字体
五、おわりに
第四章 教科書に用いる仮名字体―往来物における濁音仮名からみえるもの
一、はじめに
二、往来物の字体
三、濁音専用仮名字体の歴史
四、『てら子の友』における濁音仮名
四・一 『てら子の友』について
四・二 『てら子の友』の字体
四・三 考察
五、『続世界商売往来』、『綴字篇』、A grammar of the Japanese written language
五・一 『続世界商売往来』の字体
五・二 『綴字篇』における濁音仮名表
五・三 A grammar of the Japanese written languageの濁音仮名
五・四 考察
六、おわりに
第三部 明治期読本における平仮名字体意識の形成と変容
第五章 明治期のいろは仮名
一、はじめに
二、教科書におけるいろは仮名
二・一 調査範囲
二・二 調査内容
二・三 調査結果
二・四 議論
二・四・一 ゆれのある仮名
二・四・二 非いろは仮名とその資料
二・四・三 異版の問題
二・四・四 江戸期との相違
三、明治初期のゆれ
四、先行研究に報告された『単語篇』・『小学入門』・『読方入門』・『日本読本』のいろは仮名の字体について
五、おわりに
第六章 明治検定期以前の読本の仮名字体
一、はじめに
二、仮名字体と文献
二・一 往来物
二・二 蘭学文献
二・三 自由発行期読本
二・四 調査表期読本
三、分析
三・一 分析の視点
三・二 分析結果
三・三 考察
三・三・一 往来物と読本
三・三・二 蘭学文献と読本
三・三・三 自由発行期読本と調査表期読本
三・三・四 蘭学と異体仮名
四、おわりに
第七章 異体仮名表のかたちと字体
一、はじめに
二、異体仮名表の歴史
三、読本における異体仮名表の位置づけ
三・一 自由採択期の読本
三・一・一 『絵入智慧の環』
三・一・二 『小学入門』乙号
三・二 検査済表期の読本
三・二・一 『読方入門』
三・二・二 若林虎三郎『小学読本』巻三
四、異体仮名表の字体
五、おわりに
附 調査した読本
第八章 いろはならざる画一化のゆくえ―「かなのくわい」の画一化試案
一、はじめに
二、「かなのくわい」以前
三、「かなのくわい」における平仮名字体意識
三・一 「つきのぶ」と「はなのぶ」
三・一・一 「つきのぶ」
三・一・二 「はなのぶ」
三・二 地方支部
三・三 「ゆきのぶ」
三・三・一 「いろはくわい」「いろはぶんくわい」時代
三・三・二 「ゆきのぶ」時代
三・三・三 「かきかたかいりようぶ」以降
四、資料略解題
四・一 いろはくわい「ぶんのかきかた」
四・二 かなのくわい ゆきのぶ「かなぶんのかきかたについて」
五、おわりに
附 一、「ぶん の かきかた」
附 二、「ぶん の かきかた」
第四部 小学校令施行規則第一号表に到るまで
第九章 明治検定期読本における字体の画一化過程
一、はじめに
二、明治期の国字問題と教科書の歴史
三、『読書入門』と『尋常小学読本』との字体
四、民間版読本の字体使用の変遷
五、ふたつの検定意見
六、おわりに
第十章 小学校令施行規則第一号表を読みなおす
一、はじめに
二、本文について
三、贅注
三・一 本条の対象について
三・二 「仮名及其ノ字体」
三・三 第一号表の意図について
三・四 帝国教育会国字改良部仮名決議との関係
三・五 第一号表の字体
三・六 第一号表のその後
三・七 坊間の翻刻
四、おわりに
第十一章 例に示す仮名と実際に用いる仮名の一致について
一、はじめに
二、大槻文彦の仮名字体観
三、読本における異体仮名表と本文の仮名字体の不一致
四、異体仮名表から異体仮名の摘記へ
五、仮名字体の画一化を求める声
六、おわりに
第十二章 「いろは」から「平仮名」へ
一、はじめに
二、近世の「平仮名」
二・一 文学作品
二・二 文字研究書
二・三 外国人による記述
二・三 小結
三、近代における「平仮名」
三・一 近代文法書における「平仮名」
三・二 国字改革運動における「平仮名」
四、平仮名の指すものの変化
第五部 おわりに
第十三章 議論の整理と今後の展望
補論 平仮名字体記述法の批判的検討
一、はじめに
二、文字の認知
二・一 ひとは文字をどのように読むのか
二・一・一 いかにして文字は文字として現出するのか
二・一・二 字体の同定
二・一・三 文字から語へ
二・二 ひとはどのように文字を書くのか
二・三 字体史研究への示唆
三、平仮名の字体記述のありかたをめぐって
四、平仮名字体の構造とその記述
四・一 平仮名字体の構造と用語
四・一・一 画
四・一・二 字体と抽象文字
四・一・三 音類仮名
四・一・四 変体仮名という語
四・二 平仮名字体の記述
五、おわりに
附録 調査した読本と異体仮名導入
参照文献
後記
索引
第一章 明治期読本の平仮名字体意識の諸問題
一、はじめに
二、明治期の日本語について
二・一 明治期の文字
二・二 近代の語彙・文体と表記
二・三 明治期の識字
二・四 明治期の言語改革論
三、明治期の平仮名について
三・一 明治期と江戸期の対照
三・二 読本以外の出版物における仮名字体
三・二・一 明治期の新聞における字体
三・二・二 明治期の雑誌における字体
三・二・三 小括
三・三 読本における仮名字体
四、明治期の読本について
四・一 読本の時代区分
四・二 読本と仮名字体教授の歴史
四・二・一 前史
四・二・二 自由発行期
四・二・三 調査済教科書表期
四・二・四 検定期
四・二・五 小括
五、おわりに
第二章 いろは仮名の来しかた―近世・近代における平仮名字体の体系化
一、はじめに
二、いろは歌とその仮名
三、近世までの平仮名の体系と非体系性
四、近代初等教育でのいろは仮名と体系化
五、活版印刷における字体数削減と仮名の画一化
六、おわりに
第二部 近世の仮名字体意識の諸問題
第三章 江戸期のいろは仮名
一、はじめに
二、先行研究
三、いろは歌手本の仮名
四、君臣歌の字体
五、おわりに
第四章 教科書に用いる仮名字体―往来物における濁音仮名からみえるもの
一、はじめに
二、往来物の字体
三、濁音専用仮名字体の歴史
四、『てら子の友』における濁音仮名
四・一 『てら子の友』について
四・二 『てら子の友』の字体
四・三 考察
五、『続世界商売往来』、『綴字篇』、A grammar of the Japanese written language
五・一 『続世界商売往来』の字体
五・二 『綴字篇』における濁音仮名表
五・三 A grammar of the Japanese written languageの濁音仮名
五・四 考察
六、おわりに
第三部 明治期読本における平仮名字体意識の形成と変容
第五章 明治期のいろは仮名
一、はじめに
二、教科書におけるいろは仮名
二・一 調査範囲
二・二 調査内容
二・三 調査結果
二・四 議論
二・四・一 ゆれのある仮名
二・四・二 非いろは仮名とその資料
二・四・三 異版の問題
二・四・四 江戸期との相違
三、明治初期のゆれ
四、先行研究に報告された『単語篇』・『小学入門』・『読方入門』・『日本読本』のいろは仮名の字体について
五、おわりに
第六章 明治検定期以前の読本の仮名字体
一、はじめに
二、仮名字体と文献
二・一 往来物
二・二 蘭学文献
二・三 自由発行期読本
二・四 調査表期読本
三、分析
三・一 分析の視点
三・二 分析結果
三・三 考察
三・三・一 往来物と読本
三・三・二 蘭学文献と読本
三・三・三 自由発行期読本と調査表期読本
三・三・四 蘭学と異体仮名
四、おわりに
第七章 異体仮名表のかたちと字体
一、はじめに
二、異体仮名表の歴史
三、読本における異体仮名表の位置づけ
三・一 自由採択期の読本
三・一・一 『絵入智慧の環』
三・一・二 『小学入門』乙号
三・二 検査済表期の読本
三・二・一 『読方入門』
三・二・二 若林虎三郎『小学読本』巻三
四、異体仮名表の字体
五、おわりに
附 調査した読本
第八章 いろはならざる画一化のゆくえ―「かなのくわい」の画一化試案
一、はじめに
二、「かなのくわい」以前
三、「かなのくわい」における平仮名字体意識
三・一 「つきのぶ」と「はなのぶ」
三・一・一 「つきのぶ」
三・一・二 「はなのぶ」
三・二 地方支部
三・三 「ゆきのぶ」
三・三・一 「いろはくわい」「いろはぶんくわい」時代
三・三・二 「ゆきのぶ」時代
三・三・三 「かきかたかいりようぶ」以降
四、資料略解題
四・一 いろはくわい「ぶんのかきかた」
四・二 かなのくわい ゆきのぶ「かなぶんのかきかたについて」
五、おわりに
附 一、「ぶん の かきかた」
附 二、「ぶん の かきかた」
第四部 小学校令施行規則第一号表に到るまで
第九章 明治検定期読本における字体の画一化過程
一、はじめに
二、明治期の国字問題と教科書の歴史
三、『読書入門』と『尋常小学読本』との字体
四、民間版読本の字体使用の変遷
五、ふたつの検定意見
六、おわりに
第十章 小学校令施行規則第一号表を読みなおす
一、はじめに
二、本文について
三、贅注
三・一 本条の対象について
三・二 「仮名及其ノ字体」
三・三 第一号表の意図について
三・四 帝国教育会国字改良部仮名決議との関係
三・五 第一号表の字体
三・六 第一号表のその後
三・七 坊間の翻刻
四、おわりに
第十一章 例に示す仮名と実際に用いる仮名の一致について
一、はじめに
二、大槻文彦の仮名字体観
三、読本における異体仮名表と本文の仮名字体の不一致
四、異体仮名表から異体仮名の摘記へ
五、仮名字体の画一化を求める声
六、おわりに
第十二章 「いろは」から「平仮名」へ
一、はじめに
二、近世の「平仮名」
二・一 文学作品
二・二 文字研究書
二・三 外国人による記述
二・三 小結
三、近代における「平仮名」
三・一 近代文法書における「平仮名」
三・二 国字改革運動における「平仮名」
四、平仮名の指すものの変化
第五部 おわりに
第十三章 議論の整理と今後の展望
補論 平仮名字体記述法の批判的検討
一、はじめに
二、文字の認知
二・一 ひとは文字をどのように読むのか
二・一・一 いかにして文字は文字として現出するのか
二・一・二 字体の同定
二・一・三 文字から語へ
二・二 ひとはどのように文字を書くのか
二・三 字体史研究への示唆
三、平仮名の字体記述のありかたをめぐって
四、平仮名字体の構造とその記述
四・一 平仮名字体の構造と用語
四・一・一 画
四・一・二 字体と抽象文字
四・一・三 音類仮名
四・一・四 変体仮名という語
四・二 平仮名字体の記述
五、おわりに
附録 調査した読本と異体仮名導入
参照文献
後記
索引